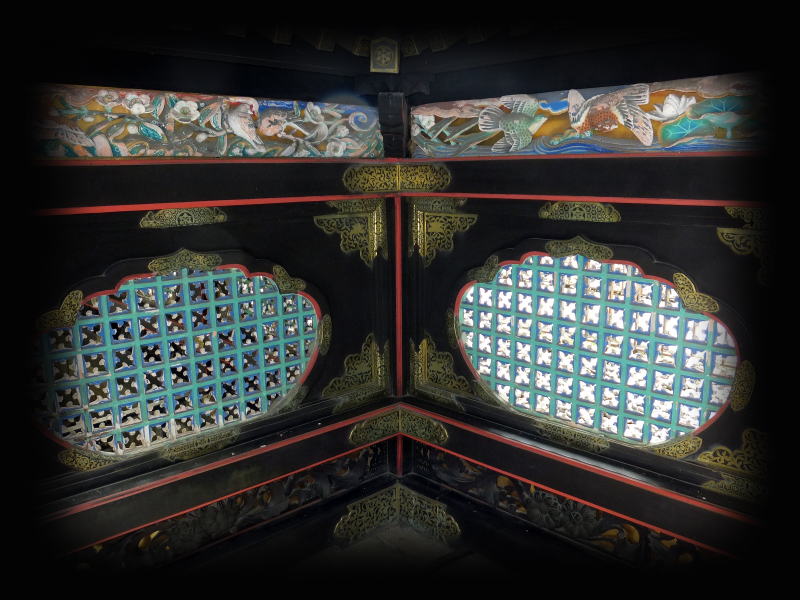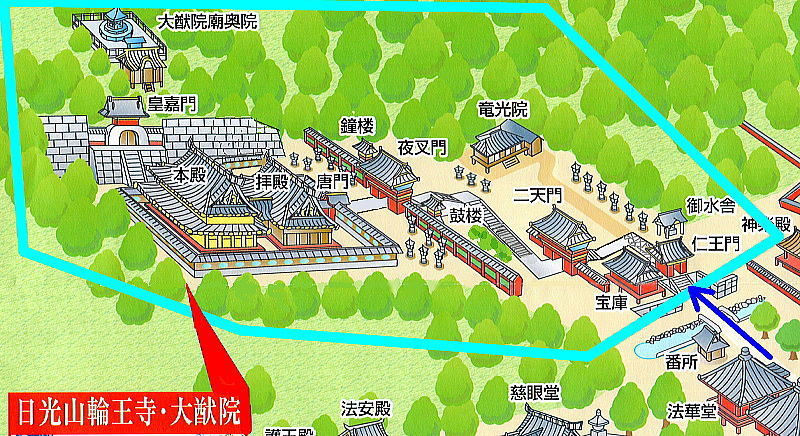
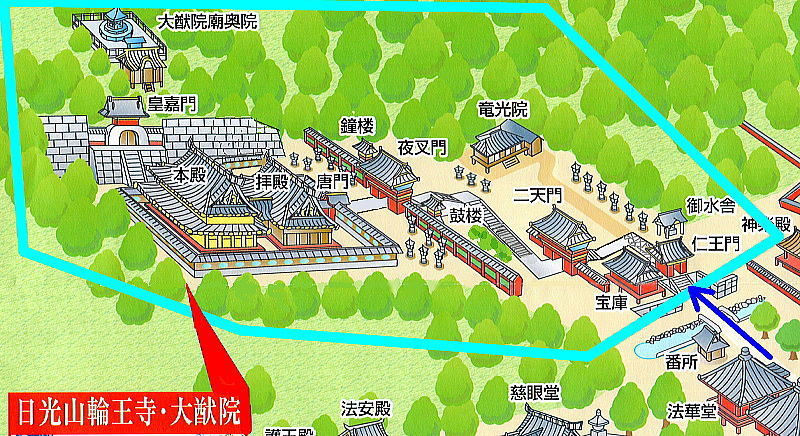
−eof−
完
↓風神:その恐ろしげな表情に、暴風に対する人々の畏れ(おそれ)が現れています。
手の指は4本で、東西南北を、また足の指は2本で天地を表しているそうです。
風 神
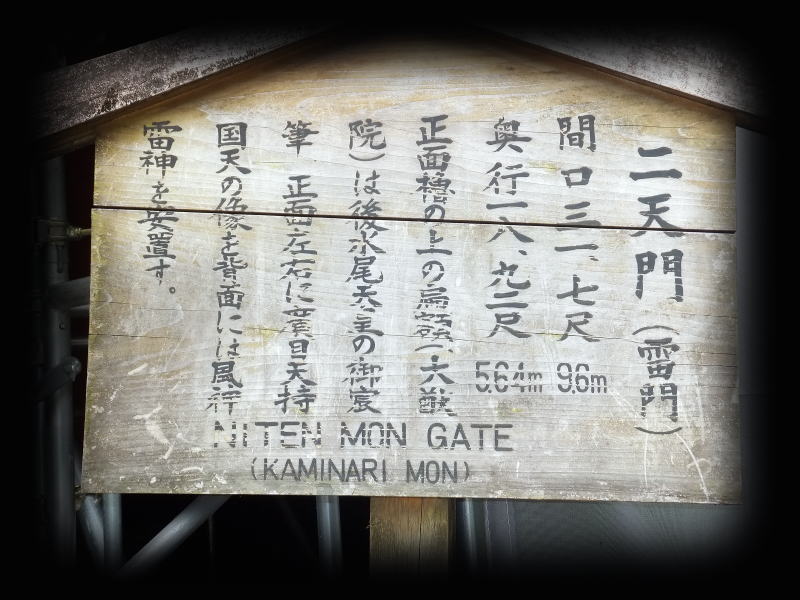
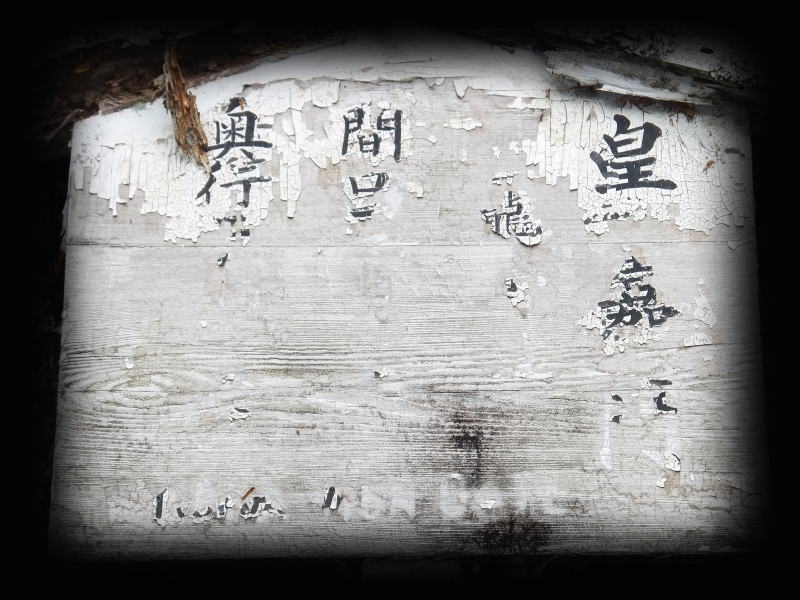



拝殿・唐門
鐘 楼
鼓 楼 (左側)
鐘 楼 (右側)
天上界からの眺め
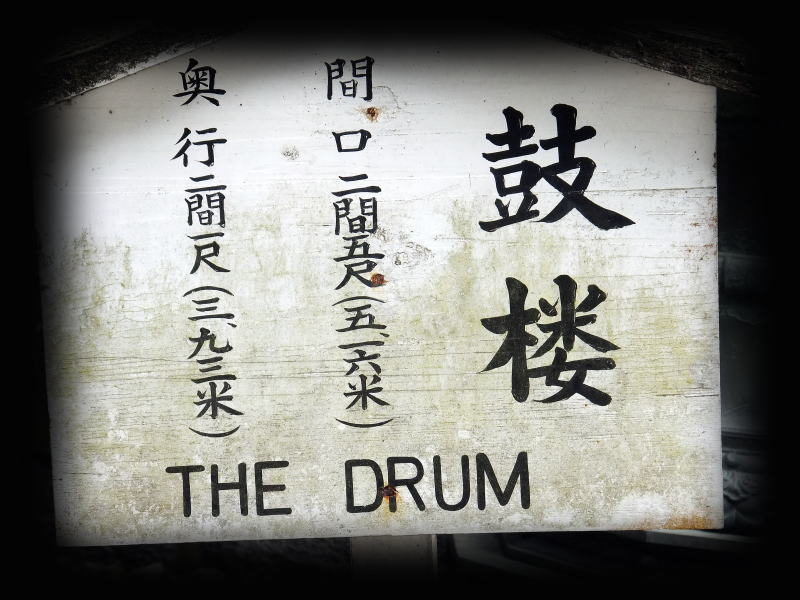

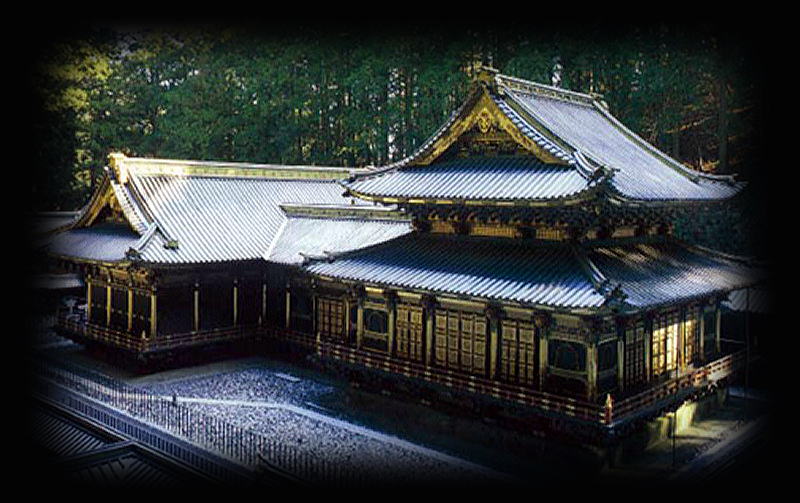


仁王門(におうもん)
初めにくぐるこの「仁王門」の左右には「金剛力士像」がまつられています









大猷院廟(たいゆういんびょう) 本殿(ほんでん) 裏手から撮影
↑ 手摺り

夜叉門・・・背面

拝殿の内部(撮影禁止)は細部に至るまで金箔が施され、文字通り金箔玉楼となっています。
寺院は本尊が南を向くのが定式で、家康公の御廟である東照宮もそのような造りになっています。
ところが大猷院の本殿は東北(鬼門)を向いているのです。
これは家光公が「死して後も朝夕東照大権現(家康公)の側でお仕え奉る」と遺言し、御廟も
東照宮の方へ向けてあるからなのだといわれています。
それでは大猷院のご本尊はどちら向きかといいますと、本殿の奥壁の裏に実はもう一つ部屋が
設けてあり、そこに釈迦三尊画像が後ろ向き(南向き)に掛けられています。
定式と遺言のどちらにも沿う妙案と言えるでしょう。
水盤舎のすずやかな音夏に入る (夢扇)
↓ 雷神:この神は水利や日照りを支配するとされ畏れ(おそれ)られた神。
手の指は3本で、過去、現在、未来を、また足の指は風神と同じく2本で天地を
表しているそうです。


大猷院廟(たいゆういんびょう) 本殿(ほんでん) 国宝 世界遺産
日光市輪王寺・「大猷院」(たいゆういん)は、徳川三代将軍「家光公」の廟所(びょうしょ=墓所)です。
境内には、世界遺産に登録された22件の国宝・重要文化財が、杉木立の中にひっそりと
たたずんでいます。
入り口の「仁王門」にはじまり、家光公墓所の入り口に当たる「皇嘉門」(こうかもん)まで
意匠の異なる大小6つの門で、境内が立体的に仕切られております。
門をくぐるたびに景色が転換して、あたかも天上界に昇っていくような印象を受けます。
夜叉門・・・背面
夜叉門・・・背面
夜叉門・・・正面
鼓楼(くろう・ころう)・鐘楼(しゅろう・しょうろう)は、寺院で時を報ずる太鼓や鐘を懸けた楼のこと。
鼓楼と鐘楼は相対して講堂の左右や楼門の左右に建てました。
↓ 修復工事中 平成26年ごろ完了予定です・・・背面より撮す
(左手石段を上がれば、夜叉門へと続きます)
雷 神
二天門(にてんもん) (雷門・かみなりもん)
重要文化財 世界遺産
仁王門を潜って左に折れると、大きな二天門を仰ぎ見ることが出来ます。
重要文化財に指定され、桜門下層正面左右に、持国天、広目天の二天を安置していることから
二天門と呼ばれています。
背面には風神・雷神が配置された均整の取れた美しいこの門は、上部分と下部分の彩色が著しく
異なっており日光の建造物では他に例がありません。


夜叉門(やしゃもん)
重要文化財 世界遺産
二天門を潜り、続く石段を左手に曲がり見下ろすと、後にしてきた灯籠や水屋が見渡せます。
ここからの眺めは天上界からの眺めにたとえられています。
いよいよ聖域へと近づいてきました。
次は霊廟への最初の入り口となる夜叉門です。
切り妻造りで、正背面に軒唐破風を付けた低平な落ち着いた造りながら、鮮やかな彩色が
目を引く華やかな門です。
正面、背面の左右柵内に「毘陀羅(びだら)」「阿跋摩羅(あばつまら)」「ケン陀羅(けんだら)」
「烏摩勒伽(うまろきゃ)」の「四夜叉」を納め、霊廟の鎮護に当たっています。
欄間、扉の羽目板部分、壁面などに流麗な牡丹唐草彫刻が施されていることから、牡丹門とも
呼ばれています。
夜 叉 門

唐門(からもん) 重要文化財 世界遺産
皇嘉門(こうかもん) 重要文化財 世界遺産
本殿の後ろ、大猷院の最も奥に位置する家光公の御廟へは、この「皇嘉門」から入ります。
中国、明朝の建築様式を取り入れたその形から、一名「竜宮門」とも呼ばれてる美しい建物です。
門を潜るときに見上げると、天上には「天女の画像」が描かれており、これから先が家光公の
御霊を奉る聖域であることを象徴しています。
門の名前は、「陽明門」と同じく宮中の門の名を戴いています。
↓ 「皇嘉門」はこの奥、右手にあります。
拝殿に続く本殿の最奥部、「厨子(御宮殿/ごくうでん)の中には、今回宝物殿で初公開中の
「家光公座像」と「御位牌」が、又その前後には、家光公の本地「釈迦如来」(非公開)が
奉安されています。
この建物を「廟(びょう)」といい、参り墓を意味し、一般の方々の正式な参拝所となります。
金・黒、赤の彩色をくまなく施された外観は、別名「金閣殿」の呼び名があるほど豪華で、
江戸芸術の極みを示しています。
鼓 楼
鐘 楼
鼓楼・鐘楼 (くろう・しゅろう)
二天門を潜り、続く石段を左手に曲がり見下ろすと、後にしてきた灯籠や水屋が見渡せます。
ここからの眺めは天上界からの眺めにたとえられています。
いよいよ聖域へと近づいてきました。
次は霊廟への最初の入り口となる夜叉門です。
二天文(雷門)正面 ・・・ 背面に風神雷神が安置されています
水盤舎(すいばんしゃ)(水屋)
四方の柱は、3本づつあり、その内の角柱4本は「八角形」です。
広目天像
持国天像




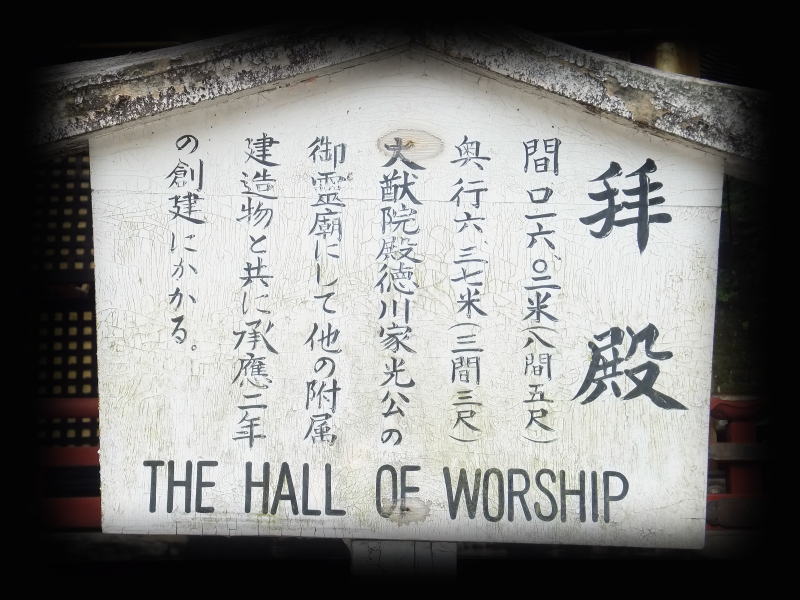


大猷院廟(たいゆういんびょう)拝殿(はいでん) 国宝 世界遺産
大猷院の中心伽藍で、拝殿・相の間(あいのま)・本殿から構成されています。
写真の拝殿は、東照宮の権現作りをそのまま生かし、規模は小さくとも細部の
技法に力を尽くした造りとなっています。
東照宮が「権現造り」を中心とした神仏習合形式であるのに対し、大猷院廟は
「仏殿造り」の純仏教形式となっています。
夜叉門を潜り拝殿の前、大猷院の中心に位置するのが以下の「唐門」(からもん)です。
その名のように唐破風を持つ、一間一戸の小規模な門ですが、隅々まで繊細な彫刻と金、白を
基調とした彩色が施されており、その意匠装飾は大変気品のあるものです。
柱や貫・梁には七宝・麻の葉などの細かい地模様が彫られ、扉には上に鳳凰、下に唐草、前後の
破風の下には雄雌の双鶴と白竜などの彫刻で余すところ無く、美しく装飾されています。
両側の袖塀の羽目には多くの鳩が彫られ、百間百態の群鳩とされています。